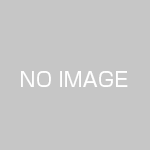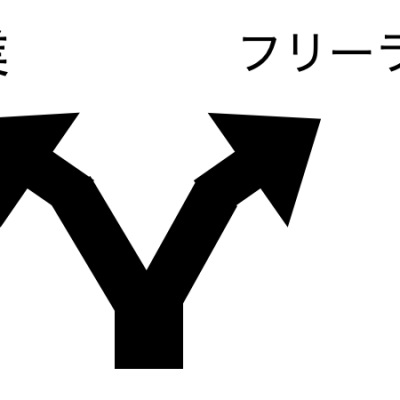たこ焼き屋が儲かった社長は、すっかり気を良くして、今度は北新地の定食屋を買った。それこそ、ピアノ弾きやホステスのお姐さんが腹ごしらえに来る店。
どうして売りに出ていたのかはわからないが、経営難だったと聞いた。たこ焼き屋に続き、この店を立ち上げるのが次の俺の仕事になった。
社長は料理番のおじいさんのみ残し、従業員は全員クビにした。
若かった俺は驚いて社長に聞いた。
俺「全員クビにして、この店やっていけますか?」
社長「覚えておいたほうがいい大事なことを教えてあげるよ。
こんないい場所で、この店は潰れかけていた。
それは、やり方が悪いからだ。悪いやり方を覚えた従業員に違う方法を言うと必ず、以前と違う、と文句をいう。
こっちにはそういう議論をしている暇はない。カネを出しているのは俺だ。さっさと立ち上げなきゃいけない。だから申し訳ないが全員クビなんだよ。いくらかは余計に払ったよ。」
この社長の言葉は、その後知ったビジネス界でも鉄則であった。
残ったおじいさんは実はとんでもないユニークな人だった。唐津さんっていったっけな。大阪の新地では当時、伝説の爺さんだった。70歳過ぎで20代、30代の愛人がいたのである。なおかつ、通りを歩いていてよくナンパしていたそうだ。無類の女好き。不動産だかで財を成したが、女にカネをつぎ込んで零落し、この店の料理番。でも、俺の和食の師匠なのであった。
関西で料理屋をやるのは厳しい。
東京に来て愕然としたことがある。関西ではお金を払うものはうまくて当たり前なのだ。なぜならばおいしいものを作るためにお金はいらない。
「高い食材=うまい」という公式はなく、うまいのは料理屋のノウハウ。それにお客はお金を払うわけで、安いからまずい、は関西ではまるで言い訳にならなかった。
当時、140円の立ち食いのかけうどんでも、店にもよるがめちゃくちゃにうまいところはいくらでもあった。
何十年も前だけど東京に移ってきて、東京の人が「おいしいから高くて当たり前」って言ったのは驚きだったし、今でもまったく納得できない。そんなこと言っている店があったとしたらプロじゃない。
店はとくに、新地で働く人が身銭を切って食べるので、季節に応じた庶民の定番が好まれた。
好色爺さんに怒られながら、いろんなものを作った。ご飯、味噌汁、おでん、粕汁(大阪の冬では定番)、天ぷら、煮物、ぬた、土手焼き等々。
好色爺さんと作っていて覚えたことは、売り物の料理は手間かけてなんぼ、ということだった。例えば、しじみの味噌汁を作る。信じられないかも知れないが、ゆでたしじみの汁を捨てる店は少なくない。別にもってきた味噌汁に貝を具としていれるだけならば、そのほうが効率的なのだ。でも、それじゃぁこういう身近なわかりやすい食べ物は「おいしくない」のである。
安くても、ちょっと一手間かけるのが商品としての料理だった。
でも、作らないものもたくさんあった。トンカツ、サラダ、お新香などなど。
理由は単純で、量産効果が高く、安く仕入れられるものは作らないのである。トンカツなんかはおもしろく、大きさが一定していないので食べやすいように切って皿に乗せて、乗りきれず余ったものでまた皿を作ってた。
私はお昼、仕込みを目一杯頑張り、夕方になって店をあけてからは別のバイトに引き継いでいた。
翌日、出勤すると、昨日の残りがいくつかある。基本的になんでも火はとおっているが、小料理屋のくせに俺が一日経ったものは衛生面から、ほとんど捨てることにしていた。
というか、料理の数は多彩に見えても食材を絞るようにするのが、安い料理屋のノウハウである。好色爺もそこはよくわかっていたのである。
好色爺が決めるメニューは季節のもので安く、かつ、無駄がなかったのである。自分が食いたいものなんて関係なかった。例えばカレーなんてものはなかった。
好色爺が言っていたことは、飲食店経営ではまともなことばかりで、おそらく前の経営者はこの人のいうことをほとんど聞かなかったのだと思う。
話は少し脱線するが、飲食店で意外に悩ましいのが余った食材なのだ。素人には焼き鳥屋が向いているというのも、技術がひとつだけでいいというのもあるが、焼き鳥屋は仕入れる食材の種類がすごく少ないので食材があまりにくいのである。
一日たって味が染みすぎて真っ黒になったおでんの大根なんてものは、商品にならなということで、ありがたくまかないで食べた。
コストは押さえ、味は向上、いや普通になったためお店は食べに来る人が増え、やっていけるようになったのであった。新地の舞台裏のような店であった。
実際のお客では、店を開けたらすぐに来るピアノ弾きのおじさんしか知らない。いろんな人を見て見たかったが、残念ではあった。
ついでながら、ここはゴキブリが出ていた。マクドナルドでバイトしていた俺基準では許せない。で、徹底的に掃除した。社長も掃除道具は快く買ってくれた。やっぱり当時は若かったので自分が食べたくない環境には、舞台裏であってもしたくなかった。ガンガン掃除して黒い床は元の床材の色になったが、ゴキブリは出る。じっと見ていた好色爺に、「隣からくるやさけ、あきらめや」といわれ、ゴキブリ退治はあきらめた。でもお椀とかの陰に隠れてるんだよなぁ。
半年も飯を作り続けたろうか、私は就職シーズンとなり引退したのだった。
あの不思議な仕事から20年後に訪れてみたがライター店もたこ焼き屋も小料理屋もまったく忘れ去られ消えていた。同時に大阪の活気も消え、こちゃこちゃとほこりっぽさばかりが目立つ通りになっていた。
三店も儲かる店をもってしまった社長はおそらく調子に乗りすぎて、やらかしたのだと思う。
私の不思議な料理人としてのスタートはきれいになくなっていて、ちょっとさみしかった。