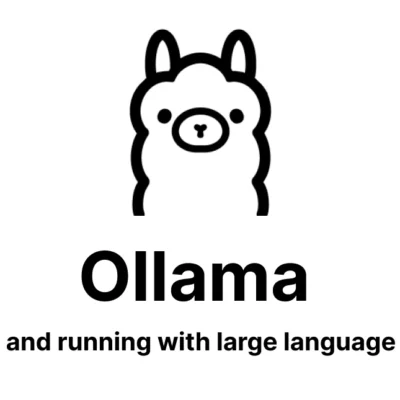AIの進化そのものについてのメモ。
実はAIがブームになったことは、過去にもあった。
年寄に限って、当時のAIと今のAIの区別がついていないのではないだろうか?
少し書いておく。
1980年代にはエキスパートシステムとしてAIが流行した。このころのAIは「ルールベース」と呼ばれ、if-then-を大量に書くことでAIに自動判断させようというものだった。具体的には炊飯器などが例としてあげられていたな。
新しモノ好きな人はAE(AI Engineer)としてルールベースを作り上げることが商売になると考えていた。
なぜ廃れたかというと、ルールを手作業でもれなくすべて記述することが現実的ではなかったからである。
一方、当時、すでに脳のニューロンを模したニューラルネットワークは知られていた。応用した機械学習による図形認識もテストされていた。が、発展しなかった理由は学問の問題よりも「機械学習させたAIの決定に誰が責任をもつんだ?」だった。
私の知る限り、この問題は現在も解決していないと思う。
2020年代に入ってからのAIは機械学習が主流だ。だがそれは素人にやらせるととんでもないことが起きることがわかってきた。
よく例にあげられる話だ。
ハスキー犬と狼の区別をAIに教えこんでいた。学習後、テストしてみるとどうも反応が思わしくない。
よくよく調べると、用意したデータのハスキー犬の写真にはすべて雪が映っており、狼のほうにはなかった。AIは雪に注目してしまっていたのだ。
この。よくよく調べないと原因がわからないところが、現在のAIの扱いの難しいところだ。
LLMなどで大規模データを扱っているとハルシネーションという現象が起きることは知られている。いわゆる嘘回答だ。
この原因を追求することは簡単なこともあれば、難しいこともある。
にもかかわらず学生のレポートを「AIがAIが書いたと判断した」などと決めつけることは、AIの使い方を知らなさすぎる。
そもそもLLMは言葉のつながりを確率で把握している。確率には100%でなければ絶対はない。
日本人はとくに確率に弱いので誤用も今後増えるだろう。
というヒストリーで今回は終わる。