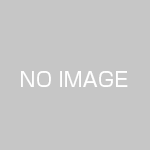40年以上昔、高校で弓道をやっていた。
そのころ、すでに古流の弓術は消えつつあった。
今、弓道として主流の小笠原流は武術としての弓術とはほど遠いところにある。
礼法にそった精神修養のための弓である。
弓道といえば明治時代にドイツ人によって書かれた「日本の弓術」が有名だが、あの本の師匠は精神修養としての弓を教えている。
大学の弓道は邪道である。精神修養もへったくれもない。当てなければ試合にならないので、「当て射」と言われるくらい弓道のやり方を各自が崩す。矢が当たらないで悩んでいる大学生、高校生は、若かりしころの私が調べた以下をよく読んで研究してほしい。
弓術の中に答えはある。精神修養の弓道の中をいくら探しても答えはない。弓道の中に答えがほしいならば「日本の弓術」を読み、せいぜい我流に陥ることだ。
戦場であたらない武器なんて意味ないじゃないか、と高校生のころの私は疑問をもち、古流を調べたのだった。
予想どおりというか、当てる方法なんてとっくにご先祖様達が開発していた。
あれから何十年も過ぎ古流の弓術は失われたかと思っていたら、どっこい生き延びていた。
これぞ、武術としての弓術である。
戦争大好きだった日本人の先祖が磨いた技術が残っている。安藤先生、淡々と語っておられるがすごい。
かけは二本がけをつかうこと。引ききっていないことにも注意。
ついでに小笠原流でない、日置流の弓術のビデオも発見した。
弓の引き方も合理的なのだが、勝手(右手)の肩を見てほしい。小笠原流のように動かさない。固定する。
高校のころ、やってみて気付いたのだが、勝手を固定すると命中率はメチャメチャあがる。
小笠原流の教えるとおり、目一杯引ききることは棒の両端がグラグラした状態で的を狙うのと同じだ。見た目はいい。
しかし片方は固定して反対側だけを的を狙うのと、どちらが合理性があるだろうか?
そして体験的に知っていることは右肩を固定して打ったほうが「矢が重い」つまり的の貫通力があがる。理由はよくわからない。
和弓は洋弓と比べて多くの人が疑問に思うことが多いはずだ。
たとえば、洋弓は的が小さく、かつ中心にいくほど点数が高い。一方、和弓は霞的と呼ぶが的にあたればいい。場所によって点数の違いがない。これでわかるとおり和弓のほうが命中率は悪い。
和弓は大きく、洋弓は小さい。弦が長いとどうしても空気抵抗を受ける。したがって、矢の射出速度は洋弓のほうが早い。
ここまで書くと和弓は劣った武器に思える。
しかし、日本で弓は「矢ぶすま」という言葉があるとおり、集団で一斉に撃つ。したがって命中精度はあまり問題にならない。
むしろ弦が長く、矢に対して比較的長く力を与え続けるので重い矢(鉄製の鋭い矢じり)がついた矢でも問題なく飛ばせる。
殺傷力が高いのだ。
日本の武器や防具は日本の戦争でそれなりに鍛え上げられてきたもので、一概に西洋式が優れているとはいえない。
なんせ戦国時代くらいまで、我々のご先祖様達は首刈りが好きなバーサーカー(狂戦士)だったのだから。