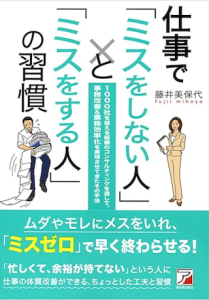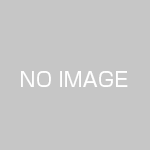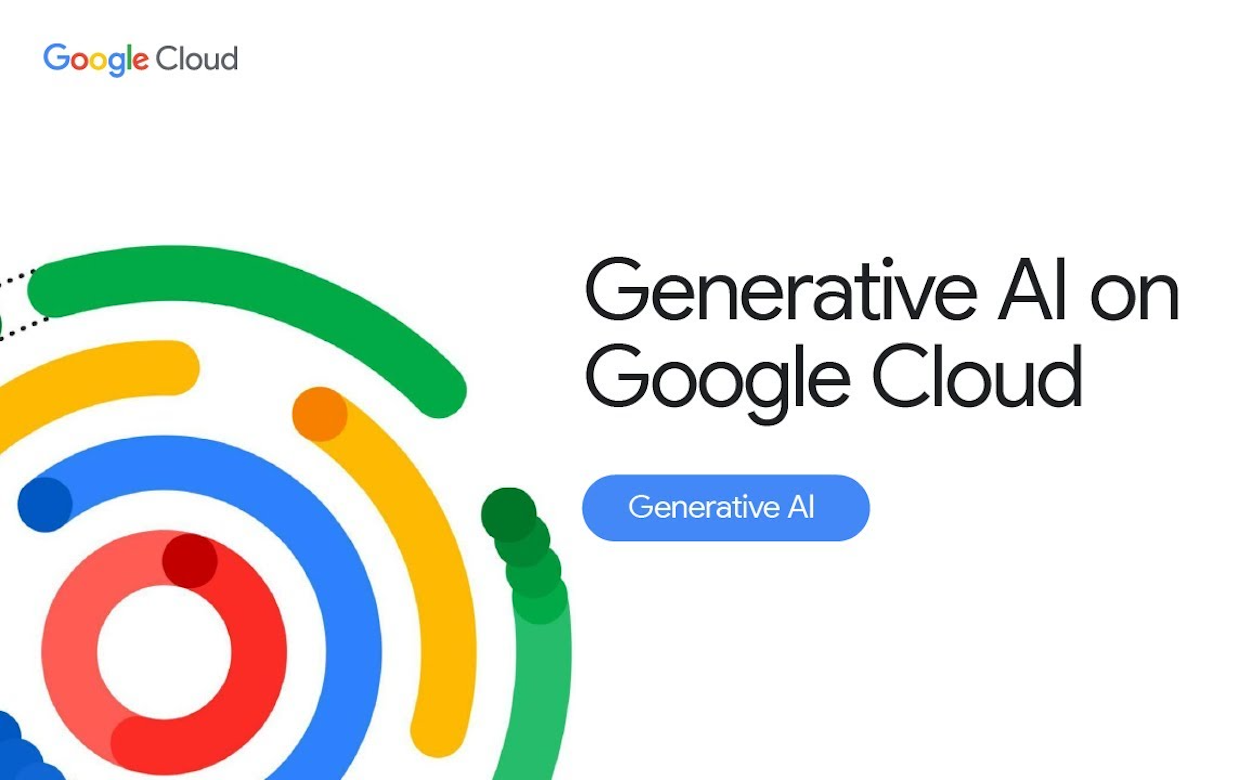ずーっとIT系エンジニアをやっているので「ミス対策」は考えねばならないことです。
読んでいただいて仕事の「ミス」について考えが変わって欲しいと願っています。
今日の毎日新聞に「鉄道7社「ミス懲戒せず」」という記事がありました。記事によると、鉄道会社がミスについて大きく方針を変えたのはJR西日本で起きた福知山線脱線事故だったようです。若い人は20年前の古い事件なので知らないと思うので、ちょっとだけ状況を説明します。起きた場所は兵庫県尼崎駅の手前です。事故が起きた電車は宝塚と尼崎の間を走っていました。この区間は阪急電車も走っており、乗客の取り合いだったのです。ですからJR西日本は少しでも早いということをウリにしていました。しかしJRはそれを運転手に押し付けるばかりで、会社としてはなんの手立てもしていなかったのです。結果として列車は加速しすぎてコーナーをまがれず、マンションに激突。乗務員乗客107人が死亡。562人が重軽傷という日本で起きたことか?という大事故となりました。
当時のJRでは列車運転手はミスをすると「日勤教育」と呼ばれる懲罰を課していたそうです。はい、よくある「おのれがたるんどるから起きるんじゃ。目ぇ覚ませぇ。喝!」という精神論です。死亡した運転手はそれが怖くて恐怖のあまりチキンレースに飛び込み、乗客を道連れに亡くなってしまったのです。
これだけの大量に人が亡くなる事故になると「おのれがたるんどるからじゃ」で済ませていいのか?ということになります。読んでおられる方によく考えてほしいのです。同じミスであっても影響度の度合いでたるんでいるで済ますのか、システムを作るのか対応を変えることでいいのでしょうか?
私が許せないこんな本があります。
おすすめしないのでリンクは貼りませんが、出版時はベストセラーになりました。
いかに日本のサラリーマンが「仕事のミスは個人の問題」と考えていることが明らかになった本です。エンジニアの観点からすると、原始人クラスです。おそらく5000年前にピラミッドを建設した現場監督のほうが、ミスについての見識は高かったと思います。
システムエンジニアは違うことをします。
遠い昔、30年以上前ですが私は日本IBMで富士銀行(今のみずほ銀行)担当営業所のSEでした。仕事のひとつが銀行のシステムで起きるトラブル、その対策と対策が行われたかをトラッキングする係でした。トラブルはお客さんの中堅の偉い人が提起、対策は会議で決める。進捗は担当者と私が確認するというやり方です。IBM側はSE部長が代表です。東大出たことが自慢の鼻毛を生やしたパワハラオヤジでした。 営業所の隅で同僚と慰め合ってました。私だってけっこうパワハラ受けてます。
このように現象の大小を問わず対策を打っていくというやり方は、高い信頼性が必要なシステムをもっている会社なら必ずやっているはずです。やらなければトラブルが頻発し、そのうち対外的にもわかるような大きなトラブルが発生します。それはハインリッヒの法則として知られています。
ハインリッヒの法則とは、1件の重大事故の背景には29件の軽微な事故、そしてその背景には300件のヒヤリハット(事故には至らないが危険な状態)があるという法則です。これは、事故発生の前に多くの危険要因が存在し、それらを早期に発見し対策することで重大事故を防ぐことができるという考え方です。
ミスを個人のせいにして解決したつもりでいると、ハインリッヒの法則に復讐されるということを知ってください。そして人類はミスを防ぐ手段を確立していることを知ってください。
それは会社の費用を大幅に削減することにもなるのです。
ところがいまだにこんな記事が流れます。
ミスの説明も謝罪もなし」「何十年と続いた発注が途切れた」若手の育成に頭を抱える上司たちの悲鳴。分断の加速が進む5つの要因
少子化です。優秀な人が欲しいならそれだけの仕事と報酬を用意しないと入ってくるわけないです。一般企業は入ってくる人の質をどうこう言える状況ではないのに、こんなないものねだりをしている人がいること自体、驚きです。
ミスはシステムで防ぐものであって、犯してしまった人の精神論にしていたら、いつまでたっても解決しないどころか、大事故が起きます。
一番理解できない人は、会社の管理職です。
部下のミスを見て文句いうだけで、なんの対応策も練らないなんて管理職の職責を果たしていないと私は考えます。なによりも個人攻撃ばかりしていたら、会社が組織として動きません。
これが「プレイングマネージャー」が管理職としては無能だという根拠のひとつです。
でも、そもそも会社の人事部が管理職教育をサボるせいだと思います。