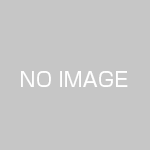この記事
に笑ってしまった。
語り手はなんと「3Dコンサルタント」。こういうヒゲをはやした輩にはロクなのはいない、という偏見を私は持っている。
で読むと、私の偏見をさらに強めてしまった。要するに「俺がぁ」なのである。
別に3Dプリンターの発展に寄与したわけでもないし、職人でもない、彼がクリス・アンダーセンのMakersと無関係なのがお気に召さないようだ。なぜならば、日本の職人は技術が高いといいながら、そのこだわりについては重箱の隅をつついているとくさし、結局は自分のショールームがベストだと言っている。
3Dプリンターの発展になにも貢献してはいないが、一人前のことはいう。
Makersが大事なことを言っているのは、こういう小うるさいオヤジを放っておいて素人が好きなものを作れるからである。そもそもタイトルが大馬鹿で「3Dプリンターは何でもできる“魔法の箱”じゃない」そんなの当たり前。
誰もそんなこと思ってないだろ。3Dプリンターで超合金のフィギュアは作れないですよ。
私自身も興味ないし。
でもアキバ界隈で3Dプリンターで作れなかったフィギュア作って喜んでいる人がいるのは事実だし、それがまたなにかを作り出すことも事実。3Dプリンターで型を作ることも可能だろう。それも製作している若者たちは、オヤジにささいな3Dの知識でいじめられずに仕事ができる。
真面目な話をすると、3Dプリンターは世の中を変える象徴である。
ちょっと前までは小さい工場でも小ロットは相手にされなかった。いまでもある。
先日、木製の箱が必要になり、ネットで6,7箇所問い合わせた。大半が田舎の工場である。そういうところはまだ都会の洗礼を受けていないため、小ロットで依頼すると、まず「できない」から始まる。ところが、新橋に事務所を構える製作所は、まず「やります」から始まる。この差である。
都内で仕事をしていたら、3Dプリンターで単品が作れるといった話を知ると、自分たちが追い詰められているのを知る。そのため小ロットでも仕事をし始めるのである。大田区のとある車の電装品の下請けはいまや半分以上の注文が小ロットになったという。技術の進歩は「ものづくり」とかいって、自分の地位にあぐらをかいている工場を淘汰するのである。