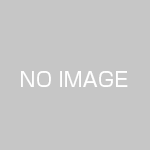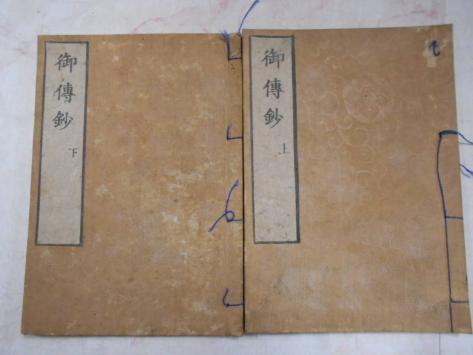ものすごく久しぶりに文藝春秋を買った。今年の芥川賞を読みたかったからである。
が、購入して机の上に置くと、遠い父の記憶が戻ってきた。
父は文藝春秋を定期購読していた。それは、本屋さんがバイクで運んできてくれるのである。子供のころに楽しみだった「科学の子供」もそうやって届けられた。
文藝春秋は子供の私には、字が小さくびっしり書かれた大人の読む本だった。それが父の文机の上に置かれていたことを思い出す。
少し長じて、少しだけ読む気力が出てきて中を見たが、老舗の鰻屋とか、年取った爺さん同士が同級生とか現実としては理解できるが無縁の世界だと思った。
久しぶりに文藝春秋を読んでも同じような記事が並んでおり、子供のことを思い出してしまった。なにもかも変わったように感じる世の中で変わっていないものに出会うと、ふっと時の流れというものを実感してしまう。
さて最初にニート歴数十年という田中慎弥氏の「共喰い」を読んだ。昭和63年という時代設定からすでに違和感があった。1988年である。この時代には、いくら九州地方でもこんな無法地帯はなかった。公害闘争もとうに一段落し、どうしようもないドブ川なんてなかった。描かれる世界は横溝正史や西原理恵子が「ぼくんち」で描いているような時代に感じた。その中でのどうしようもない暴力、エッチ、貧乏の話しなんだが、もっと凄惨な話しはいくらでも昔はあったので、とくにショックを感じることもなく、「これはなんの伏線だろう?」と思っていたら、そのまま終了してしまった。
自分は二度と読まない作家だな。
次に円城塔氏の「道化師の蝶」を読んだ。多言語作家「友幸友幸(ともゆきともゆき)」と彼の生きた跡を追いかけるA・A・エイブラムスの記号に満ちた小説。これも、さまざまなシーンを取り上げておいて、いわゆるオチがよくわからない作品だった。ウンベルト・エーコや荒俣宏系なんだろうな。